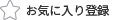- 所在地:和歌山県
- 病床数:700床
- 看護師数:925名
赤十字職員としての使命を胸に、心のかよった最良の医療を提供し、地域社会に貢献します。
教育・研修

「看護技術研修」と「病棟ローテーション」で成長できる! それぞれの教育背景を考慮しベストなカリキュラムを毎年ブラッシュアップ。独自教育の魅力をそれぞれの視点で語ります。
【新人】観察とチームワークの大切さを学んだ6週間
中学生の時にドラマの影響で看護師の仕事に興味を持ったことがきっかけとなり、この道に進みました。母が介護士をしていたことも、医療に携わる仕事を選ぶ後押しになったのかもしれません。当医療センターへの就職を決めたのは、和歌山県内の急性期病院の中でも高度急性期医療に携わる中核病院であることに加え、実習で術後の看護を経験させてもらった際に確かなやりがいがあったからです。急性期病院は忙しさもありますが、そんな中でも患者さんと密にコミュニケーションを図ることができ、手ごたえを感じられたのが決め手になりました。
入職後は2週間の「看護技術研修」を受けた後、3つの病棟を2週間ずつ回る「病棟ローテーション」へ。私は脳外科病棟、呼吸器内科・外科病棟、さまざまな診療科に対応する全室個室の特別室病棟を経験しました。ローテーションでは、日勤の先輩方にプラスワンとして入り、一緒に看護を行いながら病棟ごとの特徴を学んでいきます。どの病棟でも患者さんを観察することが必須となり、私は正常・異常を見分けるためのバイタルサインの測定を任せていただきました。特に印象に残っているのは特別室病棟です。循環器、呼吸器、消化器など、さまざまな疾患を抱える患者さんが入院するこの病棟は、毎日担当が変わるため、臨機応変な対応が必要不可欠。知識、経験が足りない私は不安なことはすぐ先輩に相談し、一つずつ解決しながら看護にあたっていました。病棟の先輩はもちろんですが、看護部新人育成委員会の方が定期的に巡回してくださり、困っていることがないかを尋ねてくれるのもとても心強かったです。
「病棟ローテーション」を終えた6月から配属病棟での看護が始まりましたが、改めて患者さんの観察が重要だと感じています。点滴、内服の確認、日常生活の支援など、いろいろな役割を担っていますが、患者さんの安全を守るためにはまずは観察!研修で身につけたバイタルサイン測定の経験を生かしながら頑張っているところです。もともと興味のあった呼吸器内科での仕事はやりがいも大きく、入院当初は苦しそうだった患者さんが回復する姿を見るたび、うれしくなっています。今後は一人でできることを増やし、患者さんにも周りの人にも頼りにされる存在になりたいと思います。
〈南館2階病棟(呼吸器内科・感染症等混合病棟)/堺 円花さん 2024年入職〉
 「急性期は大変な面もありますが、接する患者さんの数だけ成長できます」と堺さん。
「急性期は大変な面もありますが、接する患者さんの数だけ成長できます」と堺さん。
【指導者】答えではなくヒントを与える指導に注力
私が入職した当時はまだ「病棟ローテーション」はなく、他部署を知る機会はほとんどありませんでした。今回、初めて指導者になり、私自身も「病棟ローテーション」について学ばせてもらい、改めて「自分の時にもこれがあれば……」と羨ましく思っています。「病棟ローテーション」のねらいは配属前に複数の病棟を経験することで、自部署のほかにどんな病棟があり、そこにはどんな患者さんがいて、どんな治療が行われているのかを知ることです。限られた期間・限られた診療科での経験にはなりますが、私たち指導者はできるだけその病棟の特徴的な看護を経験してもらえるよう工夫しています。
また、年々高まっているのが病棟全体で新人看護師を育てようという雰囲気です。指導者も相談に乗りますが、やはり少し年次が離れているため、気軽に話せないこともあるかもしれませんよね。そんな時に新人さんと私たちの懸け橋になってくれるのが、1~2年上のエルダーです。去年、一昨年まで新人看護師だった彼ら、彼女らなら気兼ねなく相談でき、自らの経験も踏まえてアドバイスできると考え、配置しています。エルダーから上がってきた情報をもとに指導者が課題解決への道筋を示すこともあり、エルダーは新人さんの教育に欠かせない存在となっています。
それともう一つ、当医療センターが注力しているのが新人看護師それぞれの性格に応じた細やかな育成です。同じ処置を同じように指導しても、得手不得手があり、成長スピードもさまざま。だからこそ一人ひとりとしっかり向き合い、なぜそれができないのかを一緒に考えることを大切にしています。特に心がけているのは、最初から答えを与えることはせず、ヒントを出して自分で考え、アクションを起こしてもらうことです。自分で導き出した行動から生まれた成功体験は必ず糧になりますからね。特に今年の新人さんはとても前向きで、顔を合わせると「あの処置、うまくいっています!」と報告してくれるのがうれしいところ。みんなの成長を見るたび「頑張っているな」と元気をもらい、私自身の指導も間違っていなかったんだとモチベーションが上がります。
〈南館2階病棟(呼吸器内科・感染症等混合病棟)/角石 朱里さん 2019年入職〉
 複数疾患を抱える患者さんも多く、病棟ローテーションでの学びは必ず役に立ちますよ。
複数疾患を抱える患者さんも多く、病棟ローテーションでの学びは必ず役に立ちますよ。
【教育担当】一人ひとりと向き合い、大切にする教育を
これまでの教育研修のあり方をベースに、新人看護師の皆さんにより適した教育を行うことが教育担当である私のミッションだと考えています。当医療センターはもともと病棟全体で新人さんを育てるという考え方が根付いていますが、今回は特に「病棟ローテーション」を通じてみんなに彼ら、彼女らを知ってもらうこと、新人看護師も指導者もいきいきと仕事をしてもらうことを掲げ、教育に取り組みました。
「病棟ローテーション」には自部署以外の病棟を知るというねらいがありますが、さまざまな疾患のある患者さんを知るだけではなく、医療センター内でさまざまな役割を担う人に会い、人脈を広げてほしいという思いもあります。これは私の経験談ですが、病棟にいた時、かつて指導した看護師から申し送りを受けた際に「こんなに成長したんだ」と心からうれしく思ったことがありました。私はそんな経験を、より多くの指導者にしてほしいと思っています。指導者とともに悩み、よりよい関わり方を一緒に検討していくことで新人看護師への教育をより充実したものにできると考えています。また、新人さんが何を感じて、何を大切にしているのかをしっかり掴むことが一人ひとりに適した指導につながると感じています。このように私たちが目指す教育は、試行錯誤しながらよりよいやり方を追求するもの。もっと言えば、新人看護師の皆さんが入職する前から私たちの教育計画は始まっており、それぞれの強み・弱みを把握したうえでベストな教育ができることを目指しています。
こうした新人研修にとどまらず、継続教育にも力を入れているのも私たちの強みです。キャリア開発ラダーに則ったレベルに応じた研修、eラーニングのほか、一定のキャリアを積んだ後は「赤十字施設の看護師キャリア開発ラダー」システムに基づくさらなるキャリア形成(実践者、管理者、国際、教員の4分野でのキャリアアップが可能)が図れます。目指す看護師像に近づけるよう、さまざまな学びの場が用意されているのも当医療センターの魅力だと自負しています。
最後にみなさんにお伝えしたいのは、「人は必ず成長する」という私たちの思いです。成長スピードは人それぞれ、誰かと比べて遅い、速いと気にする必要はありません。みなさんが一人前になるまで私たちは必ず育てます。
〈看護部・看護係長/大西 香さん 2007年入職〉
 病棟ローテーションで多くの先輩と出会い「こうなりたい」と思える人が見つかります。
病棟ローテーションで多くの先輩と出会い「こうなりたい」と思える人が見つかります。
病棟全体で「共に育つ」環境を整えています。
新人看護師研修プログラムや実践的な指導では、教育担当者・実地指導者・エルダーなどを中心に多くの職員が関わり、病棟全体でみなさんを見守りながら育てます。悩みをアウトプットしやすい取り組みも行っており、メンタル面もしっかりとサポート。また「赤十字施設の看護師キャリア開発ラダー」システムでは、「看護実践者」「看護管理者」「国際活動要員」「看護教員」の4つのコースが選択可能。自分のキャリアを自分で開発できるシステムになっており、新人もベテランも一緒に成長できる環境です。
問い合わせ先
| 問い合わせ先・雇用法人名 | 〒640-8558 和歌山県和歌山市小松原通4丁目20 日本赤十字社和歌山医療センター 人事課 TEL 073-422-4171 |
|---|---|
| 住所 |
640-8558 |
| アクセス | 1.JR「和歌山」駅からバスで(約15分)日赤医療センター前下車 2.南海電鉄「和歌山市」駅からバスで(約15分)日赤医療センター前下車 |