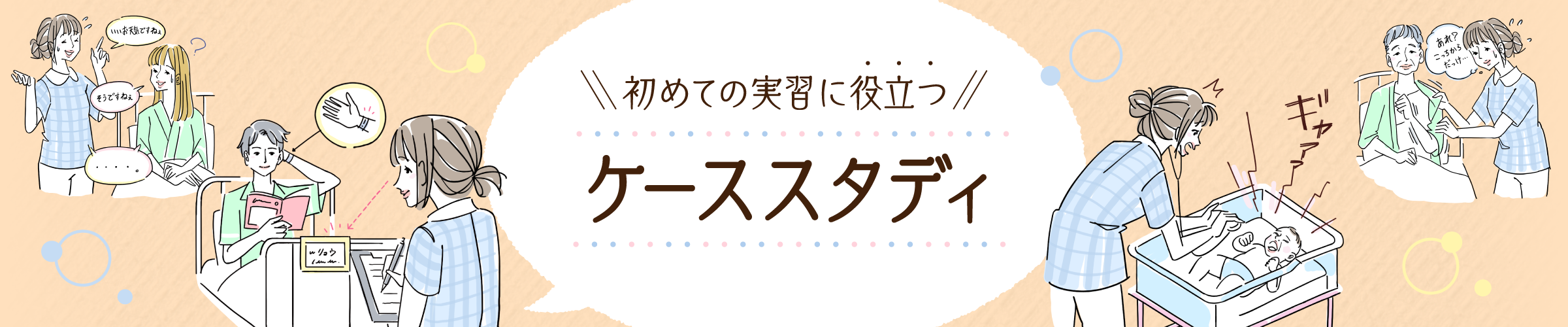
ケーススタディで
学ぶ12のルール
事前学習や記録作成で大忙しの看護実習生。
「国家試験の勉強どころじゃない!!」と焦っている人もいるかもしれません。
実は、実習中は皆さんの学力が最も伸びる時期。
じっくり取り組んで、国家試験合格に一歩近づきましょう。
INDEX
ルール.01 患者さんの名前確認
患者さんの中には病室内を自由自在に歩き回れる方もいるため、ときには、他の患者さんのベッドに座っていることもありえます。患者さんの名前を知りたいときは、腕にしている“ネームバンド”を確認する方が確実です。
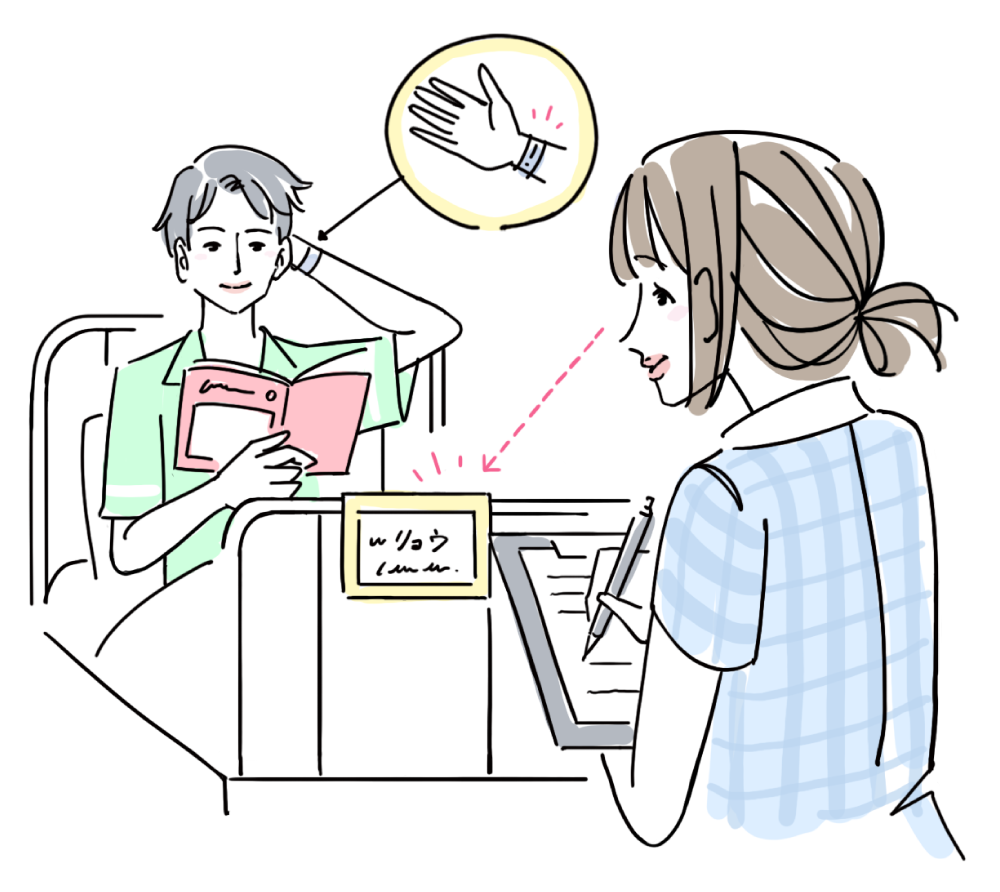
午前18問に
出題!
入院患者の本人確認の方法で最も適切なのはどれか。
- 病室でのベッドの位置
- ベッドネーム
- ネームバンド
- 呼名への反応
ルール.02 禁食中の患者さんへのケア
禁食中の患者さんのケアで、おろそかになってしまうのが口腔ケアです。「食べていないから歯磨きは必要ないんじゃないかな」と思いがちですが、口の中は雑菌が多いところ。虫歯予防のためにも、口腔ケアは経口摂取の有無に関係なく必要です。

午前17問に
出題!
口腔ケアで適切なのはどれか。
- 歯肉出血があっても実施する。
- 含嗽のできない患者には禁忌である。
- 総義歯の場合、義歯の洗浄のみでよい。
- 経口摂取をしていない患者には不要である。
ルール.03 患者さんと会話を続けるコツ
患者さんとの会話は、「退院後にやりたいことは何ですか?」というように、オープンな質問が適しています。「よい天気ですね」などの「はい」か「いいえ」で答えられるクローズドな質問では、会話がすぐに途切れてしまうからです。

午前18問に
出題!
Open-ended question<開かれた質問>はどれか。
- 「夕べは眠れましたか」
- 「薬はもう飲みましたか」
- 「傷は痛みませんでしたか」
- 「退院後は何をしたいですか」
ルール.04 老年期の患者さんの清拭
人間は老年期に入ると、身体機能が変化します。その一つが、皮膚感覚の鈍化です。清拭中、患者さんが気持ちよさそうにしていても、力いっぱいこすると皮膚がめくれてしまうこともあります。皮膚の状態を観察しながら、注意深く行いましょう。

午後5問に
出題!
老年期の身体機能変化で正しいのはどれか。
- 視野は拡大する。
- 唾液量は増加する。
- 皮膚感覚は低下する。
- 聴力は低音域から低下する。
ルール.05 新生児のバイタル測定
新生児の身体に体温計や聴診器をあてて、いきなりバイタルを測定しようとすると、赤ちゃんはびっくりして、泣きだしてしまいます。泣き声で呼吸音や心音が聞き取れなくなるので、バイタルは「呼吸→体温→心音」の順番で測りましょう。

午前5問に
出題!
入院中の乳児のバイタルサインで最初に測定するのはどれか。
- 体温
- 呼吸
- 脈拍
- 血圧
ルール.06 拘縮がある患者さんの寝衣交換
脳梗塞後の片マヒをもつ患者さんなどの寝衣交換をする場合は、健側から脱がせて患側から着せるのがポイント。頭が混乱しないように「脱健着患」と覚えておきましょう。実習はもちろん、国家試験で問われたときも、すぐに答えが導き出せますよ。

午後21問に
出題!
左上肢に拘縮のある患者の寝衣交換で正しいのはどれか。
- 脱がせるときも着せるときも右手から行う。
- 脱がせるときは右手から行い、着せるときは左手から行う。
- 脱がせるときも着せるときも左手から行う。
- 脱がせるときは左手から行い、着せるときは右手から行う。
ルール.07 糖尿病患者さんのSpO2測定
糖尿病患者さんのSpO2測定時、循環不全を起こしている部位で測ると、値が変動してしまうことを知っていますか。正確な値を得るためにも、指導者さんに測定をする部位を事前に教えてもらい、循環不全を起こしていない同一部位でSpO2測定を行うようにしましょう。

午前42問に
出題!
パルスオキシメータによる経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2>測定において、適切なのはどれか。
- ネームバンドは外して測定する。
- マニキュアは除去せず測定する。
- 末梢循環不全のある部位での測定は避ける。
- 継続して装着する場合は測定部位を変えない。
ルール.08 4歳の患児とのかかわり
4歳児ぐらいになると、看護師の説明が理解できます。痛みを感じる検査で「痛くないから大丈夫」とウソをついてしまうと、患児の信頼を失ってしまいます。正しい情報を伝えて、「ちょっと痛いけれど、10秒で終わるから頑張ろう!!」などと、励ますようにしてみましょう。

午前65問に
出題!
入院中の4歳児への倫理的配慮として適切なのはどれか。
- 採血を行う際は「痛くないよ」と励ます。
- ギプスカットの際は泣かないように伝える。
- 骨髄穿刺の際は親を同席させないようにする。
- エックス線撮影をする際は事前に本人に説明する。
ルール.09 ベッドサイドで患者さんと会話
看護師が枕元に立った状態で患者さんと会話をすると、ベッドに寝ている患者さんに威圧感を与えてしまうことがあります。患者さんとじっくり話したいときは、ベッドのそばに椅子を置いて、座って話すようにしてみましょう。患者さんも安心して会話に集中できますよ。

午前22問に
出題!
ベッドに臥床している患者との面接で適切なのはどれか。
- 枕元に立って話す。
- ベッドに腰掛けて話す。
- ベッド脇の椅子に腰かけて話す。
- 足元に立って話す。
ルール.10 外来で、リウマチ患者さんに声かけ
関節リウマチは膠原病の中で最も頻度が高く、痛みやこわばりが朝方に強くなる傾向があります。朝は外出の準備や朝ごはんの支度など、やらなければならないことがたくさんあるので、場合によっては、患者さんのご家族にサポートを依頼するなどの環境調整が必要になることを覚えておきましょう。
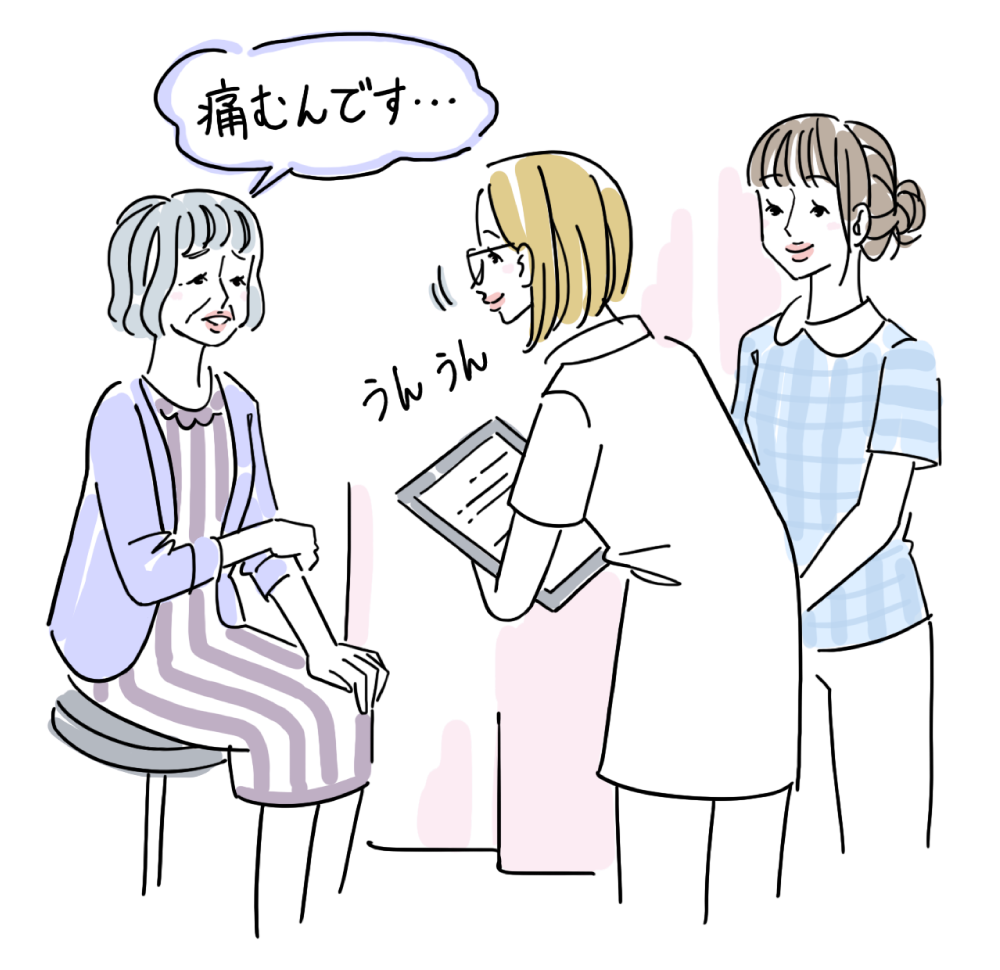
午後29問に
出題!
関節リウマチで正しいのはどれか。
- 膠原病の中で最も高い頻度の疾患である。
- 夕方の関節の痛みとこわばりが特徴的である。
- 関節炎が3か所以上に多発することはまれである。
- 関節リウマチに癌を合併したものが悪性関節リウマチである。
ルール.11 出産後の褥婦さんの援助
産褥2日目までは、母親の適応過程における“受容期”にあたります。この時期褥婦さんの心は自分自身に向かい、何かと受け身で依存的になりがちです。疲労を回復したり、分娩の振り返りが必要な時期でもあるので、まずは褥婦さんが十分に休めるような援助を行いましょう。

午前136問に
出題!
産褥1日、母親役割の獲得への援助で優先度が高いのはどれか。
- 身体の疲労回復を促す。
- 新生児の啼泣理由の判断を促す。
- 夫との育児分担の調整を促す。
- 育児技術の習熟を促す。
ルール.12 患者さんを車椅子に移乗
患者さんをベッドから車椅子に移乗するときに、特に忘れがちなのがフットレスト(足のせ台)を上げること。フットレストが下がっていると、患者さんが足をかけられずに転倒してしまう危険性があります。また、ストッパー(ブレーキ)のかけ忘れも転倒につながるので、必ず最初に確認しておきましょう。

午後21問に
出題!
車椅子による移送で適切なのはどれか。
- エレベーターを利用するときは、エレベーターの中で方向転換する。
- 移乗する前にフットレスト〈足のせ台〉を上げる。
- 急な下り坂では前向きに車椅子を進める。
- 段差は勢いをつけて乗り越える。











